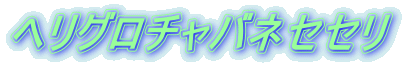
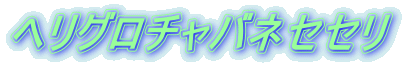
| 解説 |
| 23時55分新宿発の長野行き夜行列車は,まだ夜が明けやらぬうちに甲府盆地を通り過ぎる。多くの登山客に紛れていた高校生虫屋が降りたのは,日野春という小さな駅。背後には雑木林と田畑と草原が入り混じった,典型的な日本の田舎が広がっていた。ゼフィルスやオオムラサキで有名になったが,1970年代までは,ヒメシロチョウやゴマシジミやセセリチョウ類も多く,関東の虫屋なら一度は必ず訪れる場所だった。へリグロチャバネセセリも,線路沿いに咲く花に無心に蜜を求めていた。孵化した1齢幼虫は,葉を摂食せずに,卵が産まれた葉の凹みに繭を作り,その中で越冬するというチョウとしては変わった生態を持つ。その日野春にも,草地がもうほとんど残されていない。まだ絶滅が心配されるような種ではないが,山地草原という環境そのものが失われつつある現在では,楽観視はできない。コンビニも弁当屋もなかった時代,駅前の「アルプス食堂」と「観光食堂」で皆,腹を満たした。その二軒の食堂もいつしかなくなり,あの夜行列車も廃止された。 |
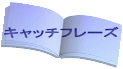
| 分布 | 北海道,本州,四国,九州 |
| 年間の発生回数 | 夏1化 |
| 食草等 | クサヨシ・カモジグサなどのイネ科やカヤツリグサ科 |
| 成虫の出現時期 | 6-8月 |
| 越冬態 | 幼虫 |