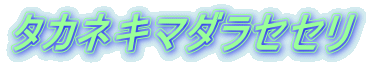
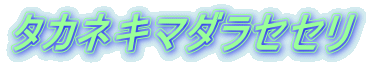
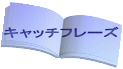
| 分布 | 北アルプス(長野県・岐阜県・富山県),南アルプス(長野県・山梨県・静岡県) |
| 年間の発生回数 | 夏1化 |
| 食草等 | イワノガリヤス |
| 成虫の出現時期 | 6-8月 |
| 越冬態 | 1年目・2年目とも幼虫 |
| レッドリスト | 南アルプス亜種(赤石山脈亜種)・絶滅危惧IA類(CR) 北アルプス亜種(飛騨山脈亜種)・準絶滅危惧(NT) |
| 解説 |
| クモマベニヒカゲなどの他の何種かの高山チョウと同様に,1世代の完了に2年を要する。本州に分布するセセリチョウ科では最も高標高地にすむ種で,北アルプスと南アルプスの標高2000m前後の亜高山帯だけに生息地が知られる。それぞれは別亜種とされ,長野県には両方の亜種が分布する。沢沿いや樹林周辺の高茎草原に生息し,様々な花から吸蜜する。圏谷のお花畑で小さな翅を精一杯に広げて朝の陽を浴びる姿は,この上もなく愛らしい。北アルプスの生息地で出会った老人は,戦後すぐから日本の高山を歩いて来たが今回が最後の山行だと告げて下山していった。タカネキマダラセセリは,一瞬飛び立ってその後ろ姿を追いかけ,また元の草の上で日光浴を続けた。南アルプスでは北アルプスよりも分布が局限され個体数は激減しているとされる。南北両アルプスを中心とした分布をしていてそれぞれが別亜種になっている種には,本種のほかにクモマツマキチョウがある。 |