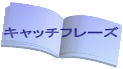
| 解説 |
| 小さいうちはベジタリアンだった幼虫が,途中から凶暴な捕食者に変わる。ワレモコウの花穂を食べて育った幼虫は4齢(または3齢)になると,地上に降り,アリの巣の中でアリの幼虫を食べて暮らすようになるのだ。幼虫は越冬して,翌年の夏にアリの巣内で蛹になる。火山の裾野草原,田畑の畔,伐採跡地,放牧地など様々な草原に生息するが,特殊な生態から生息できる条件が難しく,日本でもヨーロッパでもゴマシジミの仲間は衰亡が著しい。白馬岳周辺や白山山系の高地帯にすむものは,小型で著しく黒化することから本州中部の低山地にすむものとは別亜種とされ,「ヤマゴマ」の愛称で呼ばれる。一般に日本国内ではこれらの2亜種に加えて,「中国・九州亜種」,「北海道・東北亜種」が区分されるが,4亜種のすべてがレッドリストに掲げられている。同一亜種内でも変異は著しい。本州中部亜種は,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づく「国内希少野生動植物種」に指定され,採集はもちろん,標本の取引や譲渡も禁止されている。 |
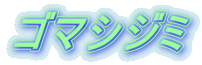
| 分布 | 北海道,本州,九州 |
| 年間の発生回数 | 夏1化 |
| 食草等 | ワレモコウ,途中からシワクシケアリの幼虫 |
| 成虫の出現時期 | 7-9月 |
| 越冬態 | 幼虫 |
| レッドリスト | 中国・九州亜種/絶滅危惧IB類(EN) 八方尾根・白山亜種(中部高地帯亜種)/絶滅危惧II類(VU) 本州中部亜種(関東・中部亜種)/絶滅危惧IA類(CR) 北海道・東北亜種/準絶滅危惧(NT) |