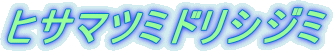
| 解説 |
| 日本のチョウの基本的な生活史は,戦後間もない1950年代初頭までにほとんど明らかになった。幼生期の生態がなかなか判明しなかった種に,ルーミスシジミ,キマダラルリツバメ,ウスイロヒョウモンモドキなどがあるが,それらも1950年代中盤ごろまでには決着がついた。このヒサマツミドリシジミの食樹が明らかになったのは,1969年から70年ごろ。懸命な努力にもかかわらず飛びぬけて生活史の解明が遅れた種で,食樹の発見に学会から懸賞金がかけられたこともあるという。人里近くの川沿いの崖に生えた数本のウラジロガシで発生していることもあるが,人手の加わった森林にすむような種ではない。雌は秋まで生き残り,9〜10月頃に産卵する。日本のゼフィルスの中で,成虫を観察するのが最も難しい種でもある。和名は発見地である鳥取県の久松山に因むが,実はこの山は「キュウショウザン」で,間違えた読み方が名前になってしまった。日本固有種。 |
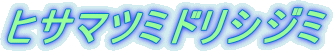
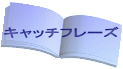
| 分布 | 本州(神奈川県・新潟県以西),四国,九州 |
| 年間の発生回数 | 夏1化 |
| 食草等 | ウラジロガシ・イチイガシ |
| 成虫の出現時期 | 6-8月 |
| 越冬態 | 卵 |