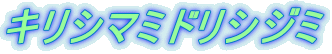
| 解説 |
| 原生林には昆虫の種類数は一般にあまり多くないが,そこに特化した種もいる。フジミドリシジミが冷温帯のブナの原生林の代表なら,ヒサマツミドリシジミやキリシマミドリシジミは暖温帯のカシの原生林のゼフィルスと言えるだろう。アカガシはカシ類の中では比較的標高の高い場所に生えることが多いため,キリシマミドリシジミも普通,低地には分布しない。戦後の拡大造林は,その時代には必要と考えられたゆえの政策だったが,それによってすみかを奪われた生き物は多い。キリシマミドリシジミは造林できなかった岩だらけの沢沿いに,辛うじて残された数十本の食樹をたよりに発生しているような場所もある。翅の表の緑と裏の銀色をきらめかせながら梢を飛ぶ姿を,誰もいない山中で見つめる時間は,チョウを趣味とする者の至福の時だ。成虫は他のゼフィルスよりもかなり遅く,7月中下旬〜8月に出現し,雌は10月ごろまで生き残ることもある。翅の表面だけでなく,裏面の色彩斑紋も雌雄でまったく異なるのは,日本のゼフィルスでは本種だけ。 |
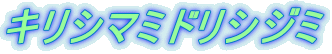
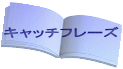
| 分布 | 本州(神奈川県以西),四国,九州(対馬,屋久島を含む) |
| 年間の発生回数 | 夏1化 |
| 食草等 | アカガシ |
| 成虫の出現時期 | 7-8月 |
| 越冬態 | 卵 |