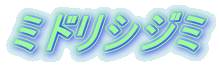
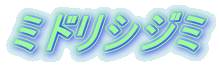
| 解説 |
| 鬱陶しい梅雨も,虫好きにとってはすてたものではない。それは,ゼフィルスたちに出会える心弾む季節でもあるからだ。北関東の平地ではハンノキが数本あれば,まず確実にこのチョウがいる。夕刻,まだ陽のあたる場所で数匹がくるくるともつれあって回転しながら飛ぶ“卍巴(まんじともえ)飛翔”は,一見の価値がある。ただし,チョウに見とれて湿地に足をとられないようにご注意。雌は多型で,原則として,前翅表に赤橙色紋を持つ型(A型),青色紋を持つ型(B型),赤青両方の紋を持つ型(AB型),赤色の紋も青色の紋もない型(O型)の4つの型がある。これは,オオミドリシジミ属 (Favonius) やメスアカミドリシジミ属 (Chrysozephyrus) の各種でも同様だが,種によっては現れる型が限定されることもある。ミドリシジミは埼玉県では「県のチョウ」。幼虫は葉を二つ折りにしたギョウザのような形の巣を作って,その中に潜む。 |
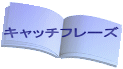
| 分布 | 北海道,本州,四国,九州 |
| 年間の発生回数 | 夏1化 |
| 食草等 | ハンノキ・ヤマハンノキ |
| 成虫の出現時期 | 6-7月 |
| 越冬態 | 卵 |