

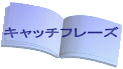
| 分布 | 本州(西南部),四国,九州(対馬,屋久島,種子島を含む) |
| 年間の発生回数 | 多化 |
| 食草等 | サンゴジュ・イヌツゲ・バクチノキ・クロキなど10科以上 |
| 成虫の出現時期 | 早春-晩秋 |
| 越冬態 | 不定 |
| 解説 |
| 太平洋側の分布北限は1980年代前半までは和歌山県から三重県付近だった。この種も徐々に分布を広げており,近年では静岡県などでも毎年記録されるようになり定着したと考えられる。関東地方でも,そう遠くない将来に普通に見られるようになるかもしれない。幼虫が樹木の蕾や花を食べていて,多化性であるために,季節によって食樹をかえていかなければ世代をつなぐことができない。春や秋には低地や山麓に多いが,夏場には標高の高い場所でも見られるようになることなどから,もともと成虫の移動性は高いと考えられる。各種の花を訪れ,吸水や鳥の糞などから吸汁する性質も強い。翅表のブルーの中央に現れた大きな白い紋が,控えめな美しさを演出する。裏面の外べりに沿った黒点列が,他のルリシジミの仲間では2列であるが本種は1列であることが大きな特徴。他のチョウが少なくなった晩秋の山あいの,放棄された茶園で吸蜜するその翅の裏面は,眩いばかりの白さだった。 |