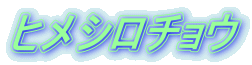
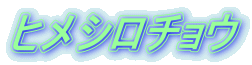
| 解説 |
| かつて農山村では,人々は自然を“守りながら使い”,そして“使いながら守って”きた。資源が枯渇しないように,適度に自然に手を加えて改変し,必要な分だけを自然からいただいていた。鎌で草刈りをしていた時代には一度に広い範囲を刈ることができず,また家畜の餌にするためには,毎日少しずつ刈る必要があった。草の伸び方が少しずつ違う部分ができて,チョウの食草や吸蜜植物が,どこかに絶えず確保されていた。ヒメシロチョウの代表的な生息地は関東地方では河川の堤防などだが,一斉に草刈りされてしまう現在では,そこは彼らの安住の地ではなくなった。古くは東京都内の練馬や杉並などからも記録があったが,減少が著しく関東地方に残された生息地はわずか。休耕田などで一時的に発生することや,火山の裾野の草原に群れていることもある。地面に止まって吸水することも多く,時には集団になる。 |
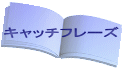
| 分布 | 北海道,本州,九州 |
| 年間の発生回数 | 多化 |
| 食草等 | ツルフジバカマ |
| 成虫の出現時期 | 4-9月 |
| 越冬態 | 蛹 |
| レッドリスト | 絶滅危惧IB類(EN) |