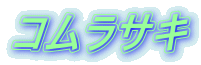
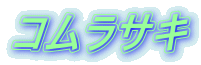
| 解説 |
| 樹液に来ている姿にも良く出会うが,獣糞で吸汁したり,夏の湿地に群れて吸水したりしていることも多い。雄の翅表の色は,角度によってまったく違って見える。その色はタマムシの鞘翅やゼフィルスの雄の翅表と同じ“構造色”。色素ではなく,翅の表面の微細構造が作り出した光の干渉による幻の色だ。クロコムラサキと呼ばれる黒色型は劣性の遺伝型で,静岡県などの中部地方や九州の一部に多いが,他の地方でもまれに採集される。中部山地の川沿いなどでは最優占種になることもあるが,南関東では一般に個体数が多い種ではない。そのコムラサキが,東京都内や神奈川県の平野部では最近分布を拡大しているらしい。幼虫は,食樹の枝の分岐部などに静止して冬を越す。標高が高い場所では,7月ごろを中心に年1回の発生になる。 |
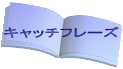
| 分布 | 北海道,本州,四国,九州 |
| 年間の発生回数 | 多化 |
| 食草等 | ヤナギ類 |
| 成虫の出現時期 | 6-9月 |
| 越冬態 | 幼虫 |