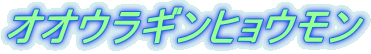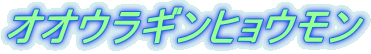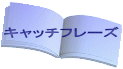| 野焼きや放牧によって維持されてきた半自然草原に強く依存したチョウ。本州,四国,九州のほとんどの都府県から記録されており,場所によっては最も多いヒョウモンチョウであったとさえいわれるが,現在では山口県と九州の一部にしか残されていない。後翅外縁のハート型の銀紋列が最希少種の証し。他のチョウが少なくなった秋の草原を優雅に舞う雌成虫には,風格さえ漂う。食草のスミレは「シバ型」と呼ばれる丈の低い草原に多く生える。しかしそれだけではこのチョウはすめないらしく,夏眠時に利用するためのススキの株などとのセットが必要だという指摘もある。半自然草原を作り,草原性のチョウの生息地を広げたのは人間だ。伝統農業が衰退してチョウの生息適地がなくなったとしても,それは人間の影響がなかった太古の状態に戻るだけだから,それでも良いのではないかという人もいる。自然災害を食い止めるために,私たちは堤防や砂防ダムを作り,河川氾濫や土砂崩れを防ぐ努力をしてきた。災害を防ぐことは必要だ。しかしそれ故に,自然に草原ができる力は,日本のほとんどの地域ではもはや失われてしまった。生息地を人為的に維持しなければ,彼らを保全することはできない。人とともに生きてきたその歴史に幕を引くのが,また人であってはならない。 |