| 解説 |
| 一日じゅう山を歩き回って疲れた足を引きずりながら帰途に着くころ,夕陽の当たるバス停でタテハチョウが活発に飛び回っている。鉄道とバスで採集に通ったあのころの,田舎道のホコリ臭さが妙に懐かしい。バス停わきのヨロズヤにはカビの生えたパンが堂々と並んでいたが,それでも何も問題は起こらなかった。今では採集に自動車を使うようになったが,珍品を狙って目的地まで歩いて行く途中で出会った普通種の方が,思い出に残っていることが多いかもしれない。ルリタテハは樹液や腐果によく集まるが,花には滅多に来ない。庭に植えたホトトギスに発生した幼虫は,いかめしい姿から不運にも踏みつぶされてしまうこともある。タテハの仲間には,翅の表と裏の色や模様がかなり異なるものが多い。主要な食樹のサルトリイバラは,西日本では柏餅を包むカシワの葉の代わりに使われることもある。科学園記録種。 |
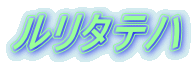
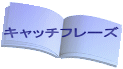
| 分布 | 北海道,本州,四国,九州,南西諸島 |
| 年間の発生回数 | 多化 |
| 食草等 | サルトリイバラ・ホトトギスなど |
| 成虫の出現時期 | 6-11月・越冬後4-5月 |
| 越冬態 | 成虫 |