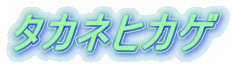
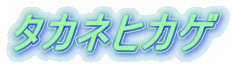
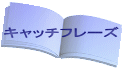
| 分布 | 本州(北アルプスと八ヶ岳) |
| 年間の発生回数 | 夏1化 |
| 食草等 | ヒメスゲ・イワスゲ |
| 成虫の出現時期 | 7-8月 |
| 越冬態 | 1年目,2年目(,3年目)とも幼虫 |
| レッドリスト | 八ヶ岳亜種/絶滅危惧IA類(CR) 北アルプス亜種(飛騨山脈亜種)/準絶滅危惧(NT) |
| 解説 |
| 日本のチョウの中で最も高い垂直分布を持つ。本州にすむチョウの中で,その全生涯をほぼ高山帯だけで送る種はタカネヒカゲだけで,その意味で真の高山チョウと言える。八ヶ岳と北アルプスの標高2400m以上の高山帯にすみ,それぞれは別亜種とされる。八ヶ岳亜種は,一時は絶滅したと考えられたこともある。山岳写真家で高山チョウの生態研究者として偉大な業績を残した故・田淵行男氏は,このチョウをハイマツ仙人と呼んだ。地面と同じ模様の衣をまとい,岩礫とハイマツの間で一生を送る仙人の姿が,一般の人の目に触れることはない。陽が射すと地面低くを活発に飛ぶが,陽が陰るとハイマツのしげみにサッと姿をくらます。卵から成虫までの発育に通常2年を要し,中には丸3年かかるものもあるとされる。本州で一般に高山チョウと呼ばれる9種のうち,コヒオドシを除く8種がレッドリストに掲載されている。高山には開発の手は及ばないが,チョウの生息に適した場所は狭い範囲に限られる。小さな環境変化が,致命的な結果を引き起こすこともある。 |