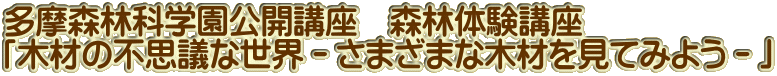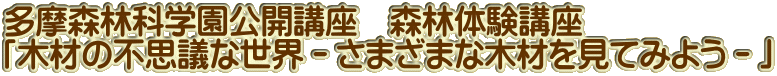
森林総合研究所では、森林や木材に関する研究を推進し、最先端の研究成果を広く現場に普及するための森林環境教育の研究を推進しています。多摩森林科学園では研究成果を広く普及することを目的に、年10回の森林講座を開催していますが、新たに体験を通じて森林や木材、自然に親しんでいただくための森林体験講座を2007年9月22日に開催しました。
森林体験講座のテーマには木材を取り上げ、地球温暖化問題につなげた内容としました。本体験講座は、木材に関する環境教育プログラム開発の研究成果の一環(科研費:19500775 「循環型社会における木材の役割を重視した木の環境学習教材の開発と実践」)として実施したものであり、さらに林野庁が推進している「木づかい運動」や木に親しむ「木育」への協力の一環でもあります。
森林体験講座の内容は、次のとおりです。
テーマ:「木材の不思議な世界-さまざまな木材を見てみよう-」
① 身近な木 -割り箸のいろいろ-
② 木は沈むの?浮くの? -いろいろな木の比重と密度-
③ 木のしくみ -立体模型づくりと木材ブロックの観察-
※プログラムの詳細はこちら(プログラムページにジャンプします)